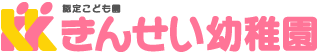「お大師さまの教育理念 」
物の興廃は必ず人による
人の昇沈は定めて道にあり(性霊集)
これはお大師さま(空海)が、平安時代の初期(828年)に「綜藝種智院(しゅげいしゅちいん)」という私立の学校を京都に創設した際、その教育理念や学校の内容を書いた「綜藝種智院式」いわゆる学則の中の言葉です。
平安時代には大学は京都に一つだけ、地方には国学といった学校があったものの、限られた特権階級(貴族)の男子でないと入学が許されませんでした。 その時代にあって身分を問わず、学ぶ意欲のある者だけが入学でき、そして先生・生徒には給与と学費を支給する完全給費制度の画期的で開かれた私立学校を設立しました。 それが「綜藝種智院」です。
余談ですが、昨年好評だったNHK大河ドラマ『光る君へ』の源氏物語が書かれたのが平安時代中期(1008年)とされていますので、「綜藝種智院」は源氏物語の180年も前のこととなります。 この時代、基本的な読み書きができるのは上流階級の人々に限られおり、読み書きを学ぶことは「手習」(てならい)と呼ばれ各家庭で行われていました。 『光る君へ』では、主人公が子供に地面に文字を書いて読み書きを教えるといった一場面がありました。
さて、冒頭の言葉は、
「全ての物事、国であれ社会であれ栄えるも滅びるも、全ては人の考えや行動による。 」
「個人が成功するも失敗するも、全てはその人の歩む道、学んだこと、生き方による。 」
という意味です。
ここにお大師さまの教育理念が現れています。 国家のみならず、あらゆる組織の栄枯盛衰は、それを担う人々によって決まる。 つまりこの世は人の力でしか変わらない。 ゆえに人が進むべき「道」というものが一番大切になります。 その「道」、指針を学ぶ道場として「綜藝種智院」を設立しました。 そこでは内典(仏教)外典(儒教)を講じていました。 開設のコンセプトは、従来のエリート官僚の養成学校ではなく、豊かな人間性、個性をもった人材育成を目指すものでした。
また、僧侶の育成においては、嵯峨天皇より高野山を賜り開創(812年)して爾来、真言密教の道場として現在まで学燈の絶えることはありません。
お大師さまの教育理念を集約すれば「生かせいのち」という言葉になります。 現在、高野山には保育連盟という組織があり、「生かせいのち」を保育現場で体現できるよう研究・研修を重ねております。 「生かせいのち」を幼年教育指針として表現するならば、「他に対するあたたかい思いやりの心を持ち、社会の一員としての責任を果たす個性豊かな人間を育成する」ということになります。 教育とは、特定のイデオロギーを喧伝し、個人的あるいは宗教的な信条を押し付けるものであってはなりません。 教育を意味する英語のエデュケーションは、個々の能力を引き出すという意味があります。 人間の持ち味を100%生かし切るための手助けをすることが、教育の本来の目的です。 はるか1200年前のお大師さんの教育理念は、現代教育にも立派に通用する素晴らしい理念なのです。
土肥義紹